


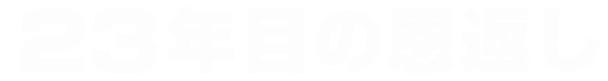

昭和48年生まれの学は、同じ年齢の騎手よりデビューが2年おそい。
それは競馬学校を自分の意志で騎手をめざして入学したものの、二度やめて2年落ちで卒業したからだ。
初騎乗は平成5年4月、19歳だった。
「あの頃のぼくはチャランポランで、どうしようもない奴だった」と、学は当時の自分をふり返る。
「ぼくは親の七光りで入ったようなもんで、未熟で、生意気だった。この話をしたら、
ぼく、涙が出てしまうんですよ」と、しばらくこらえ、目を潤ませながらこうつづけた。
「いま思うのは、あのとき、先生(父)はよく我慢してくれた。なんて強い人だろうと。
あのときはホント…いまになってね、やっと自分がどれだけまわりを苦しめたかがわかる。迷惑ばっかりかけてきました」
未熟さゆえの傲慢。男なら誰もが経験したことのある思春期のあやまちである。
デビュー当初は、レースで勝ちたい、ただガムシャラに突っ走るだけで結果は伴わない、
ガツガツしているだけの日々だった。
まわりから「田中道夫の息子」「親子鷹」と呼ばれることへの反発もあったに違いない。
素直さを失い、いらだちを抱え、苦悩の日々は長くつづいた。その頃の彼は、きっと迷子の時代だったのだろう。
そんな彼を、父親であり師匠でもある道夫師は深いふところで受けとめていた。
何も言わず、叱らず、息子の成長を待った。
息子は父親を乗り越えて成長していくものだが、父親の壁が高ければ高いほど、戸惑い、おじけづき、反抗心も強くなる。
学にとって田中道夫のハードルはあまりにも高すぎた、と想像する。
平成9年、阿部厩舎から田中厩舎に移ったとき。父親の勝負服を受け継いだ。そのときも内心では、
この服、ぼくが着たらアカンやろ、と思っていた。
「その器やないと自分でも分かっていたし、もう結構バカ息子と言われてましたしね」
迷子の時代から抜け出るきっかけとなったのは、初のリーディング獲得(平成19年)と
翌年の事故による大ケガだったという。
「リーディング争いをしだして、自分ひとりでは何もできないんやとつくづく感じました。
だから、先生にはひとつでも親孝行して、恩返しがしたい。いまはそれだけです」
インタビューで彼は自分をさらけだし、心の古傷を素直に語ってくれた。
そこに誠実さとまっすぐな人柄をみたように思う。
あの父親にしてこの子あり。情の通い合った親子の一面をうかがい知ることができたのは何よりの収穫だった。
ところで、田中学はライバル木村健をどうみているのだろう。そのことはぜひ聞いておきたいと思った。
二人は仲がいいのか、悪いのか。
タケの存在はぼくにとって大きい、と彼は言う。最近こんな出来事があった。
1月9日の笠松遠征を終えて、二人は新幹線で一緒に帰ってきた。列車の中で夕方4時半から呑みはじめ、
大阪に着いてからも十三(じゅうそう)の居酒屋をハシゴして次の日の朝5時まで呑みつづけたそうだ。
「あんな長時間、タケと二人だけで呑んで喋って笑ったの、初めてのことでしたね」。
リーディングと3000勝おめでとう、乾杯!ではじまって、それからずっと競馬の話を延々とつづけたという。
「結構、喋れるもんですね」と学は笑う。二人で本音をぶつけ、喧嘩にならず愉しく呑めたというから、
よほど気が合ったのだろう。気持ちが通じ合う同世代の騎手としてお互いが認め合っている、つまり戦友だのだ。
「あいつも園田が大好きで、まっすぐな気性でしょ。園田を盛り上げようと必死やし。
ハングリーなレースはするけど、フェアやしね。タケのことは好きです」。
ストレートで直情径行型の木村健と、おだやかで気配り派の田中学、
タイプがちがうからこそいいハーモニーを保てるのだろう。
田中道夫師が騎手時代に挙げた3164勝を抜くのは、このままいけば木村のほうが一歩早いかもしれない。
それは仕方のないことだ。しかし、3164勝を超えることの意味は木村ではなく、
田中学だからこそ特別な重みをもつのである。
かつての「どうしようもない奴」が、まもなく偉大な父を超えようとしている。
息子が父親に贈るこのうえもない恩返しだ。このまま無事に勝利を重ねていけば、
この夏、われわれは園田の新たな歴史の1ページを見ることができるだろう。
2015年は園田競馬にとって、そういう意味でも興味深い年である。
文:大山健輔
写真:斎藤寿一
