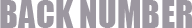「(父親と)同じ世界に入ったときから師匠と弟子の関係でしたから……
遠慮した部分がたしかにありましたね。
で、父親がリタイヤしてやっと父と息子の関係に戻れた。いまは気分がラクです」
偽らざる本音だろう。祖父の代からつづく調教師家系の三代目は、
親の保護下から解放されたかのようにすっきりした表情で胸のうちを吐露する。
忠明師が橋本忠男厩舎から独り立ちしたのは4年前の2013年10月。
翌14年には親子そろって年間60勝を挙げている。
当然、ライバル意識はあったようで「負けないよう頑張ろうと思ってやってきました」と、
忠男師が勇退するまで互いに競り合う関係を築いてきた。
開業後の成績(2013年10月開業だから実質3年半)は、60勝、53勝、55勝、
重賞4勝と申しぶんない数字なのだが、本人は「まだまだ物足りない」と言う。
「それだけの馬を預けてもらってるので、もっと成績を上げていかないとダメです」
優秀な馬を預けてもらっているわりには勝ち鞍が伸びていない、
その不満をかかえながら今後の伸びしろに期待しているといったところだ。
「今年もそうですけど、うちの厩舎は2着リーディングなんですよ。
馬が走ってないわけじゃない。走ってるのに勝ち切れていない。
どうやって2着を1着にするか――」。そこが今年の課題だと認識している。
祖父と父の仕事場であった競馬場に幼いころから馴れ親しみ、馬が大好きだった。
小学校に上がるころにはランドセルを背負って調教ルームに行き、
朝の攻め馬を見てから登校するというトラックマンまがいの毎日で、
下校後はランドセルのまま寝わらを片付けていた。すでに当時から馬で活きてゆこう、
ときめていたようだ。
高校卒業時に、将来どういうカタチで馬と関わればいいのかを考えたとき、
父親は競馬場しか知らない、それなら自分は北海道に行こうと思った。
父親と同じ馬の世界で、父親かがやったことのない仕事をやりたいという発想だった。
北海道ではJRAの育成牧場で馬の世話、鍛え方を学び、一年半後に海外に目を向ける。
アメリカで10ヵ月、アイルランドで3ヵ月、日本とはちがう競馬社会に飛びこみ、
広い視野を身につけた。転機は日本に戻りJRAの調教師をめざしていた時期に訪れる。
「園田に帰ってこないか」と父親からの電話があった。
「まあ、運命ですね。そう思いました」
高校を卒業したばかりの青年が5、6年のあいだに出遭った抱えきれないほどの
未知の世界での体験、そこから吸収したものがいかに多かったか、得たものの大きさを
忠明師はあらためて感じている。
忠男厩舎ですごした助手(調教師補佐)時代、育成牧場を馬の休養と
調整のための施設として活用するアイデアを持ち出したことなどは、
牧場での経験と人脈が役立った一例だろう。
厩舎の看板馬であるオオエライジンを育成牧場に移し、
坂路調教などでハードに鍛えたのも忠明師の発案だった。
「たしかに、ぼくがいなかったらライジンを坂路調教することはできなかった。
ぼくが提案してそれを理解してくれたところが、父親のアタマの柔らかさだと思います」
オフの時期の馬の休ませ方、調教方法に牧場を利用するやり方は
いまでこそ園田でも通例のようになっているが、その先鞭をつけたのが忠明師であった。
「これまでの園田のスタイルだと一番馬といえるような馬は厩舎から出さなかったですよ。
厩舎から出すと微妙に狂いが生じる、いい馬は厩舎から出すな!と、
ベテランの先生方から言われたものです」
育成牧場に移してリスクをかかえるよりは、自厩舎でケアするほうが安心安全であり、
当時の職人気質に合っていたということだろう。
競走馬を鍛えるうえでの重要なポイント、勘どころは「調整のむずかしさにある」と、
忠明師は明かす。「これはぼくの考え方ですけど…」と前置きして
「生き物が相手なので、技術の前に感性なんですよ。馬がどの程度仕上がっているのか、
いまがピークなのか、それは人間が思ってるだけなんです。
馬の疲れ具合をみるのも人それぞれ受けとり方がちがう。レースに向けて、
たとえば中3日で追い切りました、中4日で追い切りました、で仕上げます。
それはちょっと経験を積めばできること。問題は、そこからの微調整の仕方が、
技のある人とない人とでは差が出てくる。
そこからは感性の問題であって、感性を養ったもん勝ちだと、ぼくは思ってます」
忠明師が一目置いていたベテラン厩務員(マッキ―ローレルを担当していた)を例にとり
「いい感性をもってる人は感じ方がちがう。
だってね、攻め馬するのは同じ馬場、調整もただ何周乗るかだけの話なんで。
そこでJRAに行ってセントライト記念4着にもってくるんですから、凄いですよ」。
※マッキ―ローレル 1999年~2005年に活躍。
29戦9勝(うちJRA3戦0勝)。重賞は菊水賞、MRO金賞(金沢)。
セントライト記念(GⅡ)4着、白山大賞典(GⅢ)3着
データを重視した、システム化されがちな調整法とは逆に、
感性を軸に置いた職人的な仕上げ法に相当なこだわりを持っている。
「いまでもそうですけど、ぼくはひと叩き(重賞を想定して平場レースで調整すること)
しないんです。エーシンクリアーは去年1年間重賞しか使っていない。
レース間隔が2ヵ月空いていてもピークにもっていく自信があります」。
昨年はクリアーで重賞2勝し、それを実証した。馬の疲労度を見抜く点においても
感性が生きてくる、とみている。平場をひと叩きして中2週か3週で使うほうが、
じつは調整する側はラクなのだそうだ。
「中2ヵ月ってめちゃくちゃしんどいですよ」と忠明師は言う。
それでもこの調整法を崩さないのは馬に負担がかかるから。その信念は揺らぐことはない。
「走る馬こそ負担がかかるんで、繊細に看(み)ないといけない。
だけど遠慮してたらダメなんです。攻めるときは大胆に攻めないと。
大胆に攻めて繊細に看る」。調教で遠慮していたら走る馬も走らなくなる。
競走馬とはそういうもの。目一杯攻め馬で叩いて、調教後のケアは繊細に、
丹念に。そうして、馬の疲れ具合を感性で感じ取る。このポリシーは不変のものだという。
「だから、スタッフには感性を養えと。
馬のいろんなところを看て、鋭く感じてほしいんです」