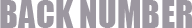1991年4月、17歳の永島太郎は初騎乗初勝利という離れ技で鮮烈デビューを飾った。
騎乗馬エルテンリュウはそれまで63戦未勝利の馬で、
ゴールした本人も周囲もただただア然…。
その後も順調に勝ち星をかさね(この年23勝をマーク)、新人賞に輝いた。
あれから27年、若武者はベテランと呼ばれる齢になったが、
いまも往時と変わらぬ姿で園田の馬場を駆け回っている。
現役を長くつづけるということだけでなく、つねに第一線に身を置き、
人気騎手でありつづける、そのパワーの源は何なのかー。
疑問をぶつけると、「勝つことですー」即座に答えが返ってきた。
「競馬を外から見ることも好きだし、もちろん乗ることも好き。
乗りこなせたという結果が出たら、それが一番うれしいですしね。
こんな魅力的な仕事はないです」
見ることも乗ることも大好き。
競馬に惚れて、レースで勝つことでさらにモチベーションが高まる。
心を揺り動かす原動力は変わらぬ”競馬愛”。
それが熱血漢でありつづけるヒケツのようだ。
新人賞を獲った永島だが、意外にも競馬学校時代の成績はよくなかったらしい。
ともに学び、同期デビューしたのが長南和宏と松浦政宏。
「3人のなかで、ぼくが一番成績も下でしたし、全然下手くそでした。
彼らに比べたら、よく卒業できたなというレベルだった」と謙虚に振り返る。
「デビューして、お世話になった緒方勝調教師が力を入れてぼくを育ててくれました。
あの時代はオーナーに頭を下げて、うちの坊主を乗せてやってくれっていうのが
まだ通用した時代だったんです。緒方先生には感謝しかないですね」
デビューして6年目(1996年)、永島は初めて100勝の壁をクリア(138勝)した。
数字だけをみれば、この年から5年ほどの期間が絶頂期といえるが、
ただ99年だけは67勝に終わっている。新年早々に大怪我をしたのが原因だった。
「ぼくほどジェットコースター人生の騎手も珍しい」と本人は笑うが、
たしかに怪我を含めた諸事情による紆余曲折の騎手人生を歩んできたことは
成績のうえからもわかる。
なかでも99年の怪我による離脱は、20代半ばの成長真っ盛りのころだっただけに
ショックは大きかったにちがいない。
「1月2日の一発目のレースで、ぼくが乗ったのは総本命の馬でした」
レース直前の返し馬で、出走馬の1頭が急に暴れ出し、永島の馬にぶつかってきた。
馬と馬の間に左脚がはさまって五指を全て骨折。
馬のあばら骨も折れるほどの大事故だった。
ちょうどこの時期が園田の”第3の男”と評された時代。
この前年、小牧太と岩田康誠がリーディング1位2位、3位に永島がしっかりつけていて
リーディングを狙える位置にいたのである。
ジェットコースターの軌道はここで下降したが、しかし翌年には106勝を挙げ、
下りから上りに転じている。
「それが20年も前なんで、大昔の話ですよね。最近の若い騎手はそんなこと知らない」
過去を懐かしむでもなく、悔しい思い出として語るでもなく、
執着なくあっさりとした表情で彼はそう言った。
永島が北海道に遠征したのが2009年7月~9月までの2カ月間。
遠征から戻った彼の変化を敏感に感じとった関係者は多かった。
「園田に戻って、まわりの人たちから乗り方が変わったと言ってもらいました。
馬を動かそうとしてる意思が感じられると。(遠征に)行ってよかったなと思いました」
上体を前後に揺らせて力強く押してゆく。並の騎手なら横ブレして馬に負担がかかるが、
中心がブレていないから馬に無理なく押せる。
大井の的場文男騎手に似ているという見方だ。
「アクションが大きいから馬が動くとは、基本的にぼくは思ってないんです。
いかに馬に負担をかけずに乗るかがベスト。
園田の小さい馬場で、深い砂で、最後のハナ、アタマを争おうと思えば、
やっぱり馬に負けないぐらい人間が押さないとダメです。
その差が結果に出る。それと、見た目を変えてやろうという意識はたしかにありました。
オーバー気味のアクションでアピールの度合いがちがうとなると、
それもひとつの自己アピールの仕方かなと」
昔といま、レースに臨む気持に変化はあるのかという質問に答えて、
「勝ちに対する思いは、いまのほうが強いかもしれない」と言う。
「昔だったら、ああ、勝っちゃったって感じですけど、勝つことのむずかしさというのは、
勝ち星の多い騎手のほうが感じてると思う」
経験を積んだ騎手であるほど、通算勝ち星が多い騎手であるほど、
1勝することのむずかしさを身に沁みて感じている、と彼は考える。
「そんなに簡単に勝てるもんじゃないですからね。みんなが勝とうと思ってるし、
ましてや走るのが馬なんで。競馬ほど思いどおりにいかないものはないんじゃないかな…。
それで思いどおりにいくレースができたときは無茶苦茶うれしい。
だから辞められないんですよね」