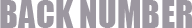この連載では騎手、調教師をこれまで多く取りあげてきた。が、今回はそうではない。
馬場でしのぎを削る勝負師たちと距離を置いたところでドラマを語る、
いわば黒子的存在の場内実況アナウンサー・吉田勝彦氏である。
この人を”ミスター園田””ミスター地方競馬”と呼んで、
それに異議を唱える人は一人もいないと思う。
競馬実況の大御所であり、頂に立つ人であり、
かつて地方競馬全国協会会長が「このアナウンサーは地方競馬の宝」と
最大級の賛辞をおくった、正真正銘の真打ちに今回は登場願った。
現在改修中の園田競馬場では、スタンドにせりだした舞台のような台上に実況エリアが設けられている。
ここ数年、吉田さんが実況席にすわる回数は極端に少なくなった。
主力は竹之上次男であり、三宅きみひとに移っている。後進に道をゆずったかたちだ。
「だけど、ぼくは喋りたいんや」
いまの状況に抵抗するように吉田さんは言う。
「喋りたいね。レースは見るより喋りたい。喋るというより、ぼくはレースを語りたいんです」
競馬実況をはじめたのは昭和30年、18歳のときだから今年で63年。
園田競馬とともに生きた歳月である。実況レース数は9万レース近く。
距離にすれば(1レースを1400mと計算して)14万4000km、地球三周半におよぶ。
レース実況は馬と騎手に教えてもらうもの、これが考え方の基本にある。
騎手を男前にするのが実況アナの仕事、とも考えている。吉田節の要諦はこれだ。
実況をはじめた昭和30年という時代は競馬はいまほど一般的でなかった。市民権を得ていなかった。
日本ダービーと秋の天皇賞をNHKが放送するぐらいで、
そんな時代だから勉強するにもテキストも手本もない。
吉田さんは厩舎に出かけ馬の世話を手伝いながら調教師、騎手、
厩務員たちの会話に耳を傾け競馬を学んだ。
朝の調教を終えた厩舎が教室だった。勉強は2年半つづいた。
「ぼくは誰に教えられたわけでもない。
すべて我流。馬と騎手に教えてもらうものだと思ってやってきた」。
走るのは馬、動かしているのは騎手。
馬と人間がつくる予測不可能なドラマ、そういう競馬というものに魅力を感じている。
「競馬を成立させるものは意見の相違である、と言った人がいるけれど、そのとおりだと思うね。
このレースはどう展開するのか。
スタート切ったときから逃げるであろうと思った馬が出おくれることだってある。
出おくれたら、そのあとどう処理するか。
騎手が思うように立て直せない場合もある。
そういう意外性がおもしろい。
自分が想像するのとちがう展開になることのおもしろさ。
それを言葉に置きかえるのはどうすればいいのか。それがレース実況のたのしさなんです」。
賭け事は一切やらない吉田さんだが、競馬のおもしろさ、
レース実況のたのしさをそんなふうに考えている。
そうして、レースは喋るのではなく、語りたいのだと言った。
「先頭どれで二番手どれで、三番手のこの馬が追い上げてきました…みたいことをいうだけで
1分半が終わってしまうんやったら、なんのために実況があるんやろと思う。
レースの動きに合わせて喋るのではなく、自分の言葉に馬がついてくるという喋りをぼくはしたい。
いつもそれを思う。
9万レース近く喋ってきて、ああ、きょうは百点満点もらえるような喋りができたやろかと思うと、
そんなのは1回もないね」
9万レースと対峙してきた男は妥協することはない。いつももがいている。
仕事を終えた夜は、にがい思いがのこる。きょうのあの馬、あそこで教えてくれていたのに、
あのとき騎手が教えてくれていたのに…
それを喋れなかった悔しさ、無念と後悔。「キザなこと言うようですけど、
昨日より今日のほうがちょっとはましに喋りたい。
そういう気持ちがあるから63年間やってこれたと思うんです」

園田競馬場を訪れる競馬好きの著名人は数多くいるが、
競走馬のオーナーとして知られる北島三郎さんも、そんな園田ファンの一人である。
園田に遊びにくると、同い年の吉田さんにサブちゃんは気さくに声をかける。
吉田さんも演歌の大御所に敬意をはらいつつ、親しみをもって接する。
何年か前、吉田さんは「もう実況を辞めようと思っている」とサブちゃんに打ち明けたことがある。
内心からこみあげる思いがあってのことだった。
いつも温厚なサブちゃんがこのときだけは吉田さんを睨みつけ、こう言った。
「吉田ちゃん、なに言ってるの。俺だって足りねぇんだよ。だから唄ってんだよ…」。
返す言葉がなかった。こんな凄い人でも「足りないんだ」という。
自分の仕事に満足していないのだという。だから唄いつづける。
プロフェッショナルとはなにか、ということに関して吉田さんは鋭敏なアンテナを持った人だ。
自らを叱り鼓舞するために、より高みをめざし自戒を忘れないために、
吉田アンテナは多角的に張り巡らされている。
「これまで自分の仕事に一度も満足したことはおまへん。
きょうは60点ぐらいか、きょうはちょっとましに語れたかなと思うときで70点。
百点満点はとてもとれまへん。まだまだ足りない」
と、生前に語った人形浄瑠璃の語り手、七代目竹本住大夫。
同じ意味の言葉を遺した女優の杉村春子。サブちゃんと同様に、芸の厳しさを説いたそうした言葉や
厳しい世界で生きぬく人間の心のありように吉田さんは心を揺さぶられるのである。
「だからね、ぼくなんか何万レース喋ってきて、これはちょっと喋れたかなと
思うレースがいくつあるか。そのことを考えるよね」
といって、後悔の残るにがいレースばかりではない。
まるで結果がわかっていたかのように吉田さんはレースを実況する、と評した人がいる。
長いあいだやっていると、自分でレースをつくれたと思える瞬間がある。
あらかじめ予測してた展開にレースがピタッとはまり、思ったとおりの運び、
駆け引きの妙を過不足なく言葉に表現できたと思えるレース。
そんな一つが1986年6月、ビクトリートウザイ(保利良次騎乗)が本命馬で出走したレースだ。
ハンデ戦で63キロを背負ってレースがスタートした。3角をまわって、先頭がビクトリートウザイ。
いよいよ直線、あとゴールまで230m。このとき、左右後方から2頭の馬が勢いよく追いこんできた。
場内に喚声とどよめきが起こる。この展開でもビクトリーの優位を吉田さんは見てとった。
「まだビクトリートウザイには余裕があります。来るなら来い!」と言葉に出して言った。
ビクトリーの逃げ切り間違いなし、そう読んだ。
このレース、俺がつくったぞ。プロの矜持である。
「来るなら来い!」のひと言が、ビクトリーの単勝を買っていた観客をどれほど勇気づけたことか。
結果は言わずもがな。こうして、ときにひと夜の美酒に酔うときがある。
「あのとき何を考えたか。ビクトリートウザイ、ありがとう。ぼくの言葉を生かしてくれてありがとう」